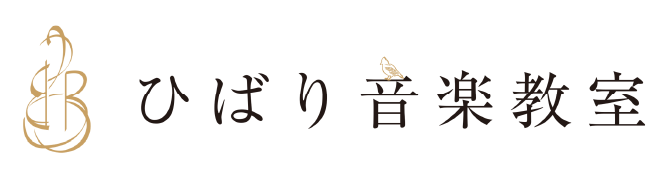先日、日本の貝類学の研究史をたどる「貝に沼る」という特別展を、大阪市立自然史博物館に観に行きました。
とても面白くて、閉館ギリギリまで居座ってしまうほどでした。江戸時代からのさまざまな研究者たちの熱意や、
展示の説明や見せ方などから、学芸員の方のエネルギーも届いてきました。
浜辺で貝を見つけると「なんていう名前の貝だろう?」と思いますが、過去の研究者たちがいなければそれには名前もありません。
彼らが様々な、本当に小さなものでも一つ一つに興味を持ち、研究して名付けてきてくれたという当たり前のことに、改めて感動しました。
私は小さな頃から貝殻が好きで、大人になって海に近い場所に住んでからは、より身近な存在になりました。
それでも、しばらくは浜辺で綺麗な貝殻を見つけて満足する程度でした。
そこからふと、貝殻になる前の貝の生態などについて考えるようになりました。
貝は何を食べるの?
二枚貝はどうやって動いているの?
いつも見かけるあの貝の名前は?
こうした疑問がでてきて、私の貝に対する本当の興味が始まりました。
音楽に対しての興味も疑問から始まったように思います。
この曲のこの部分がとても好きだけど、なぜだろう?
合唱で歌うと美しく感じるのははなぜだろう?
この瞬間に切なく聴こえるのはなぜだろう?
子どもの頃は不思議に思うことばかりだったのに、大人になると知っていることが増えていく気がして、つい見逃してしまう疑問がたくさんあります。
今回は貝の世界を覗くことで、子どもの頃のような、未知の物事に対してワクワクする感覚を味わうことができました。